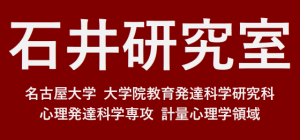研究室について
学生の研究領域
教員の研究分野が教育測定学とか計量心理学とか言われるものなので,そのような研究(テストの開発や評価など)を行う学生もいますが,データサイエンスや研究法なども扱っていることから,さまざまな領域の学生が,本研究室には所属しています。これまで在籍した学生の研究テーマを見てみると,看護,メンタルヘルス,ソーシャルサポート,パーソナリティ,認知スタイル,文章生成,動機づけ,学習方略,メタ認知など,多岐に渡っています。
臨床系の学生が本研究室に所属することも可能です。公認心理師や臨床心理士の受験資格を得るためには,大学院の精神発達臨床科学講座に在籍して所定の科目を履修することが必要ですが,その講座の学生でも,本研究室に所属することができます。実際,公認心理師,臨床心理士になって,心理職として活躍しているOB・OGもいます。
異なる研究領域の学生が同じ研究室に在籍していますので,互いの専門性を生かした裾野の広い議論をすることができます。学生の研究内容の詳細は,博論・修論・卒論題目やメンバーのページをご参照ください。
ゼミについて
学生の研究領域が多岐にわたっていることもあり,学生全員が集まる定例のゼミは行っていません。学生と教員による1対1のミーティングを随時行っています。1回のミーティング時間はだいたい1.5~2時間くらいですが,もっと長くなることもよくあります。
では,学生同士の関係が希薄かというと,そうでもないようです。小さな所帯なので,研究のことなどで何か相談しようとすると,結局みんなが関わることになります。定例のゼミがなくても,お互い何をやっているか,何に困っているかを分かっていて,なんとなく助け合ってやっています。
指導方針
本研究室では,学生による自主的な勉強・研究を奨励しています。各自の研究テーマは,基本的に学生自身が決めます。研究を進めるにあたって,教員はいろいろ言いますが,最終的にどうするかは学生に任されています。
卒論について。多くの学生にとって卒論は,1年近くもの時間をかけて,自分のペースで,好きなだけ打ち込んで,ひとつのことを成し遂げるという,希有な経験になります。ですので,学生がやりたいことができるようにと考えています。研究テーマの決定には,あえて時間をかけるようにしています。本当にやりたいことを見つけてほしいからです。
修論について。修士を出て就職しようと考えている学生については,やりたいことができるようにということは卒論と同じですが,学術的な意義を深めることも考えてもらうようにしています。進学を考えている学生については,学会誌に掲載されるレベルを目指します。研究の方向づけ,進め方,まとめ方などについて指導しますので,卒論,修論,博論の中で,一番,指導色が強いと思います。
博論について。研究の支援をするようにしています。研究内容や進み具合の相談にのったり,査読コメントへの対応を一緒に考えたり,研究環境を整えるなど,学生の研究が先に進むことを考えています。
研究環境を整えることに関連して,とくに研究職を目指す大学院生に対しては,学生のうちは学業に専念しなさいと言っています。非常勤講師などの教育活動は,就職に必要な最低限の量に留めるように指導しています(経済的理由は別途考慮します)。教えることは勉強になります。しかし,度が過ぎると,多くの時間と労力を費やし負担となります。また,負担に感じない場合は,教育することに自分の価値を認め,一人前の指導者になった気分になって,研究をおろそかにするようになります。大学教員になれば,研究したくてもできないことが多いです。研究し続けられる研究者になるためには,学業を怠らないことが大切です。
本研究室に興味関心を持たれた方は,お問い合わせのページをご参照頂き,ご連絡ください。
<先頭へ戻る> <研究・教育のページへ戻る>
修了・卒業後の進路
博士後期課程を修了した学生は,大学や研究機関の研究職等に就いています。
博士前期課程を修了した学生は,本学や他大学の大学院後期課程に進学したり,公務員や児童相談所の心理職等になっています。
学部を卒業した学生は,一般企業に就職したり,本学や他大学の大学院に進学したり,公務員になったりしています。