【 最近の論文・口頭発表等,WWWページで公開しているものもあります.また名古屋大学の機関リポジトリから公開しているものもあります.】
網羅的に上げてありますが、全てではありません.m(_ _)m
最後に更新したのは 2019.7.12 です.
ページ内メニュー
著書・研究報告書
・訳書等(共著・共訳・編訳等を含む)
- 『質的研究の考え方 研究方法論からSCATによる分析まで』名古屋大学出版会 大谷 尚 2019.3.31
- 『質的心理学事典』新曜社 2018.11.30(項目担当)
- 「これからの医療コミュニケーションへ向けて」石崎雅人・野呂幾久子・監 (2013).篠原出版新社.担当 I-第3章. 32-51.『医療コミュニケーションへのアプローチと質的研究手法の機能と意義』
- 『教育工学選書 教育工学とはどんな学問か』日本教育工学会監修、坂元昴編著、岡本敏雄編著、永野和男 編著、担当<第3章 近接領域からみた教育工学、3.3 教育学からみた教育工学>.ミネルヴァ書房 2012
- 『質的心理学講座 第1巻』無藤隆・麻生武編.2008. 東大出版会.担当 第9章 <学校文化と「神神の微笑モデル」−テクノロジーと教授・学習文化とのコンフリクト−>.233-266
- 「教育実践研究」コンピュータ利用教育協議会(編)『学びとコンピュータハンドブック』.東京電機大学出版局. 2008. 30-33
- 『質的研究ハンドブック 3巻 質的研究資料の収集と解釈』N.K.デンジン・Y.S.リンカン編、平山満義監訳、大谷 尚
・伊藤 勇 編訳 北大路書房 2006年8月
- 『人工知能学事典』共立出版
(項目担当)2005年12月
- 『教育テクノロジーと学校文化
の間のコンフリクトと交互作用に関する質的観察研究』
『平成14年度〜平
成16年度
科学研究費補助金 基盤研究(C)(2)
研究成果報告書』(研究課題番号14580214) 研究代表者
- 『現代教育方法事典』日本教育方法学会編.(項目
担当)図書文化社.2004 年
- 『教育の方法と技術』(共
著:西之園晴夫・宮寺晃夫
編著)ミネルヴァ書房
2004(担当(第2章)教育システム(組織)の新しいパラダイム
−フリースクールやホームスクールから日本の学校を考える− pp31-55)
- 『ジェンダーを科学する −男女共同参画社会を実現するために−』(共著:松本伊瑳子・金井篤子
編)ナカニシヤ出版 2004(担当(第II部 学術におけるジェンダー 7
)教育とジェンダー.189-203)
- 『学校教育におけるインターネ
ット利用の問題と課題の解明を目的とする質的観察研究』『平成11年度〜
平成13年度
科学研究費補助金 基盤研究(C)(2)
研究成果報告書』(研究課題番号11680217) 研究代表者
大谷 尚、2002年3月
- 『現代カリキュラム研究 −学
校におけるカリキュラム開発の課題と方法−』(共著:山口 満編著)学文
社
2001(担当(第3部
現代社会とカリキュラム開発、11章)情報化時代の教育課程の在り方
−新たな学校文化を創造するために−.pp138-151)
- 『学校教育におけるコンピュー
タ利用の特質,問題,課題の解明を目的とする質的観察研究』平成8年度
−11年度科学研究費補助金
研究成果報告書 1999
- 『 質的研究法による授業研究
−教育学・教育工学・心理学からのアプローチ−』(共著:平山満義
編)北大路書房
1997( 担当「教育工学からみた質的授業研究」123-181)
- 『大学授業の技法』(共著
赤堀侃司編)有斐閣
1997(担当「メーリングリストを活用した授業のサポート」48-51
、「授業内レポートを用いた受講者とのコミュニケーション」
278-281)
- 『教職研究:情報化社会に求め
られる資質・能力と指導』(共著:河野重男監修・赤堀侃司編)教育開発
研究所
1996(担当「情報を交流する能力」102-105)
- 『学校教育におけるコンピュー
タ利用を対象としたエスノメソドロジカルな研究手法の開発』(単著)平
成5年度−7年度科学研究費補助金一般研究(C)研究成果報告書 1993
- 『情報と人間』名古屋大学
放送(テレビ)公開講座テキスト(共著:名古屋大学公開講座委員会編)
1991(担当 第9章・第10章「学校教育の情報化」pp117-134)
- 『現代教育の理論と実践』(共著:小野慶太郎編)学術図書出版社
1985(担当 第3章3「教材としての映像の問題」
pp171-178)
論文・研究報告
- 大谷 尚.(2017).質的研究はどのように進めれば良いのか −しばしばなされる質問にもとづいたいくつかの具体的なガイド- .学校健康相談研究14(1) 4-12
- 大谷 尚.(2017).質的研究とは何か.藥学雑誌. 137(6). 653-658. (Symposium Review) [PDF]
- Yoko Hirayama, Takashi Otani, Masato Matsushima. (2017). Japanese citizens’ attitude toward end-of-life care and advance directives:a qualitative study. Journal of General and Family Medicine. 18(6):378-385.【Original Article】【Yoko Hirayama の博士(医学)学位論文】
- Masayo Kojima, Takeo Nakayama, Takashi Otani, et.al. (2017). Integrating patients' perceptions into clinical practice guidelines for the management of rheumatoid arthritis in Japan. Modern Rheumatology.【Original Article】(25 Jan 2017) DOI: 10.1080/14397595.2016.1276511
- 大谷 尚(2016) 質的研究とは何か −実践者に求められるその本質的で包括的な理解のために−.学校健康相談研究 Vol.13 No.1.2-13
- 大谷 尚(2016) 質的研究とは何か −その意義と方法−.日本歯科医師会雑誌 Vol.68 No.12
- 青松棟吉・大谷 尚.司会:西城卓也 (2014).座談会:医学教育研究における研究倫理. 医学教育.45(4). 249-274
- 小嶋雅代・小嶋俊久・難波大夫・茂木七香・大谷 尚他 (2013) 関節リウマチ患者は薬物治療の変化をどのように感じているか−フォーカスグループによる質的研究−.中部リウマチ.43(1).17-20
- 増永悦子, 大谷尚 (2013) がん患者遺族ボランティアによる語りの分析 -緩和ケア病棟でボランティアをする意味の解明, 日本緩和医療学会誌
- Aomatsu, Otani, Tanaka, Ban, van Dalen.(2013) Medical Students’ and Residents’ Conceptual Structure of Empathy: a Qualitative Study. Education for Health. 26(1), 4-8.
- 藤崎和彦,田川まさみ,西城卓也,井内康輝,錦織 宏,渡邊洋子,大谷 尚,守屋利佳,吉岡俊正,吉田素文,鈴木康之(2012)「日本医学教育学会認定医学教育専門家資格制度創設への提言」医学教育 第43巻・第 3 号,Vol.43,No.pp.221-231
- Saiki, Mukohara, Otani, Ban (2011) Can Japanese students embrace learner-centered methods for teaching medical interviewing skills?. Medical Teacher: International Journal of Medical Education, 33(2) 69-74
- 大谷 尚(2011) SCAT: Steps for Coding and Theorization -明示的手続きで着手しやすく小規模データに適用可能な質的データ分析手法 -.感性工学.Vol.10 No.3 pp.155-160
- 大谷 尚(2009) 「医学教育修士プログラムについて−トロント大学の医学教育学修士課程の紹介と教育学の立場からの検討−」特集/次世代の医学教育者の育成に向けて.医学教育. vol.40 No.2. 255-258
- 鈴木・吉岡・吉田・田川・錦織・西城・守屋・大谷・渡邊(2009) 「医学・医療教育学の専門家養成に関するニーズ調査結果」特集/次世代の医学教育者の育成に向けて.医学教育. vol.40 No.2. 237-241
- 鈴木・吉岡・吉田・田川・錦織・西城・守屋・大谷・渡邊(2009) 「序章」特集/次世代の医学教育者の育成に向けて.医学教育. vol.40 No.2. 235-236
- Hiroshi Nishigori, Takashi Otani, Minako Uchino, Simon Plint and Nobutaro Ban (2008) I
came, I saw, I reflected: a qualitative study into learning outcomes of
international electives for Japanese and British medical students, Medical Teacher: International Journal of Medical Education, 2009; 31(5), 196-201
- 長谷川元洋・大嶽達哉・大谷 尚(2009)ネットいじめの問題に対する学校の法的権限についての検討.情報ネットワーク・ローレビュー 第8巻.商事法務.86-97
- 谷井淳一・大谷 尚・無藤 隆・杉森伸吉・山川法子・坂本將暢(2008)劇指導者はいかにして子どもたちの想像力を引き出すのか.ルーテル学院大学・日本ルーテル神学校 紀要.Vol.42.17-32
- 大谷 尚(2008) 質的研究とは何か--教育テクノロジー研究のいっそうの拡張をめざして.教育システム情報学会誌.25(3) 340-354
- 浜田・江崎・大谷・近藤・バティ(2008)OSTE : Objective structured teaching evaluations 指導医の教え方は評価できるのか.第40回日本医学教育学会.医学教育 第40巻 補冊11
- 奥谷・濱田・バティ・大谷. (2008). カナダにおける職種間教育の新しい流れ.医学教育.38(3) 181-185
- 長谷川元洋・大嶽達哉・大谷 尚. (2008). ネットいじめに対する教師の対応の教育的・法的問題の解明と課題の検討―ある公立中学校での事例を手がかりに.情報ネットワーク・ローレビュー 第7巻.商事法務.104-113
- 大谷 尚(2008)4ステップコーディングによる質的データ分析手法SCATの提案 −着手しやすく小規模データにも適用可能な理論化の手続き−.名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要(教育科学).Vol.54.No.2,27-44 (この論文は名古屋大学機関リポジトリからダウンロードできます)
- 長谷川元洋・大谷 尚(2007)個人情報保護法全面施行後の初等中等教育機関の個人情報保護の現状と問題.情報ネットワーク・ローレビュー.第6巻.商事法務.121-133
- 大谷 尚(2006)教育と情報テクノ
ロジーに関する検討 −ハイデッガーの『技術への問い』をてがかりとして−.教育学研究. Vo.l73. No.2,別冊 14-28
- Kei Mukohara, Nobutaro Ban,
Gen Sobue, Yasuhiro Shimada, Takashi Otani, Seiji Yamada(2006),
Follow the Patient: Process and Outcome Evaluation of Medical
Students' Educational Experiences Accompanying Outpatients,
Medical Education, 40.Blackwell Publishing, Oxford, UK, 156-165
- 長谷川元洋・大谷 尚(2005)
学校における児童・生徒に関する個人情報の取扱いの実態と問題
−教員を対象としたアンケート調査を手掛かりに−.情報ネットワー
クロー・レビュー 第4巻第2号.情報ネットワーク法学会.pp
34-48
- Takuya Saiki, Kei Mukohara, Takashi Otani and Nobutaro Ban (2005) Students' Perceptions of
Learner-centered, Small Group Seminars on Medical Interviewing: a
Qualitative Study, Proceedings of 3rd Congress of the Asian
Medical Education Association (AMEA), 57
- Takashi Otani (2005) A Life
Story Study of Technology Specialist Teachers in Japan: Latent
Significance of Lack of Human Content in Educational Media and
Technologies, Piet Kommers & Griff Richards (2005)
Proceedings of ED-MEIA 2005. World Conference on Educational
Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Association for
the Advancement of Computing in Education. 100-100
(論文は全6ページ.ProceedingsはCD-ROM に所蔵)
- Takashi Otani (2005)
Reflecting on Japanese Universities' Global Citizenship
Education and Traditional Values, Virginia Stead (2005)
Proceedings: International Education Dynamics - Their Influence
and Dynamics within the Canadian Academy. http://www.csse.ca/CCSE/Conference.htm
- 大谷 尚(2005)質的アプローチ
は研究に何をもたらすか.(大谷 尚・無藤 隆・サトウタツヤ.質的心
理学が切り開く地平.pp16-36)質的心理学研究.第4号.pp17-28
- 大谷 尚(2004)人間のコミュニ
ケーションの構造とメディア −人間的なコミュニケーションへの回帰をめざ
して− 学習情報研究,2004
,9月,(財)学習ソフトウェア情報研究センター,pp15-18
- 大谷 尚(2003)質的研究と歯科
医療−質的研究は歯科医療に何をもたらすか−『日本補綴歯科学会雑誌
−第111回日本補綴歯科学会学術大会抄録集−』2003年11月,p43
- 直井一博・大谷 尚(2003)第二
言語学習のエスノグラフィの理論的枠組み
−英語合宿におおける英語学習を一事例として− 日本教育工学会論
文誌/日本教育工学雑誌
27(3), 247-258
- 坂本将暢・柴田好章・大谷 尚 (2003)発話分析のための発話のリズム分析の手法の提案と検討 −質的研
究の支援システムの開発を展望して−日本教育工学会第19回大会講演論文
集,2003年10月,
pp823-824
- 大谷 尚(2003)行動目標による
『本時の目標』の記述とその『痕跡表現』について −教育現場における教育
工学的な考え方の受容・排除・文化変容のプロセスの検証−日本教育工学
会第19回大会講演論文集,2003年10月,pp
821-822
- 中田有紀・羽谷沙織・西野節男・
大谷 尚(2003)大学の講義を通した受講者の意識変容と概念形成に関する
考察 −フィールドワークの経験を伝える『教育人類学講義?』の受講者に対
する調査
名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要(教育科学),第50巻第
1号,2003年9月,pp179-190
- 大谷 尚(2003)「質的研究と科
学教育 −質的研究は科学教育に何をもたらすか−(日本科学教育学会年
会論文集27、2003年7月,pp35-38)
- 村上 隆・吉田俊和・的場正美・
柴田好章他16名(2003)サマー・スクールの実施による高大接続の改善に関
する基礎的開発研究(特集I
高大接続のためのワークショップ「サマー・スクール2002」)『名古屋大
学大学院教育発達科学研究科 中等教育研究センタ−紀要』第3号(2)
pp1-4
- 大谷 尚(2003)トロント大学附
属学校『名古屋大学大学院教育発達科学研究科 中等教育研究センタ−紀
要』第3号(1)pp1-3
- 大谷 尚(2003)インターネット
の中の人権『愛知学院大学情報社会政策研究』ISSN
1344-9060,第5巻2号,2003年3月,pp83-97
- 大谷 尚(2002)教育工学の研究
手法としての質的研究手法 −Quantity
of Learning から Quality of Learning
へ−『日本教育工学会第18回大会講演論文集』 pp27-28
- 大谷 尚(2002)
第4章 実践研究の体系化(4.1
背景と問題提起)(4.5教育実践研究における信頼性と妥当性−質的研究を
手がかりに−)『Post
Modern
Ageにおける教育工学研究の体系化に関する総合的研究』平成12年度−13年度
科学研究費補助金基盤研究(B)(1)最終報告書(研究課題番号12480038)研究代表者
電気通信大学 岡本敏雄、2002年3月、59-60頁、75-80
- 大谷 尚(2002)
第5章 教育工学における哲学的基礎(5.1
本グループの課題とその検討)『Post Modern
Ageにおける教育工学研究の体系化に関する総合的研究』平成12年度−13年度
科学研究費補助金基盤研究(B)(1)研究成果報告書(研究課題番号
12480038)研究代表者
電気通信大学 岡本敏雄、2002年3月、89-92
- 大谷 尚(2002)
第2章 教育システム(組織)の新しいパラダイム
−フリースクールやホームスールから日本の学校を考える−『ネット
ワーク社会における教育の実践知の形成と結合による現職教育に関する研究
−ポストモダンの視点から−』平成12年度−13年度
科学研究費補助金基盤研究(B)(1)研究成果報告書 研究代表者 仏教大学
西之園晴夫、2002年3月、24-40
- 香山瑞恵、池田 満、本田敏明、 大谷 尚、松居辰則、岡本敏雄(2002)
Post Modern Age
における教育工学研究の体系化の試み『日本教育工学会研究報告集
「教育工学における研究方法論」』
JET02-1、2002年1月、67-74
- 大谷 尚(2001)
インターネットの教室利用をさまたげるものは何か−テクノロジー
vs.
教授・学習文化−『日本教育工学会第
17回大会講演論文集』17-18
- 金子大輔・大谷 尚(2001)フリ
ースクールにおけるICT利用を対象とした質的研究−ICT利用を形成する要因と
してのスタッフのテクノロジー不安と問題意識−『日本教育工学会第17回
大会講演論文集』487-489
- 大谷 尚(2001)「第3章 情報
化教育法の内容と大学での授業方法 第4節 シラバスの収集と内容の分析」
『高校普通科『情報』のための教員養成カリキュラムと教員免許の履修形
態に関する研究』平成12年度 科学研究費補助金基盤研究(C)(1)研究成果報告
書(研究課題番号12898008)研究代表者
電気通信大学 岡本敏雄、2001年3月、pp82-84
- 大谷 尚(2001)「第3章 情報
化教育法の内容と大学での授業方法 第3節 書く授業案の比較と検討による
特徴化」『高校普通科『情報』のための教員養成カリキュラムと教員免許
の履修形態に関する研究』平成12年度 科学研究費補助金基盤研究(C)(1)研究
成果報告書(研究課題番号12898008)研究代表者
電気通信大学 岡本敏雄、2001年3月、pp74-81
- 大谷 尚(2001)「第4章 教育
工学における哲学的基礎、第1節
本グループの課題とその検討」『Post Modern
Ageにおける教育工学研究の体系化に関する総合的研究』平成12年度−13年度
科学研究費補助金基盤研究(B)(1)中間報告書(研究課題番号12480038)研究代表者
電気通信大学 岡本敏雄、2001年3月、pp51-52
- 大谷 尚(2001)「情報化時代の
教育に何が求められているか」『名古屋大学大学院教育発達科学研究科
中等教育研究センター紀要』第1号、2001年3月、pp7-22
- 大谷 尚(2000)あるフリースク
ールの学校文化の検討−サドベリーバレー・スクールでの観察と面接にもとづ
く分析−『名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要(教育科学)』
47(2)2001 pp11-27
- 大谷 尚(2000)
教育実践研究における『研究仮説』を考える『IMETS』財団法人才能開
発教育研究財団、vol.4,
No.136、2000年3月、pp62-65
- 大谷 尚(2000)
SCSによる連続講義を取り入れた大学授業の開発と評価『平成
11年度研究調査助成報告書』財団法人松下視聴覚教育研究財団、2000年、
pp37-50
- 大谷 尚(2000)サドベリーバ
レー・スクールを訪問して『中部開発センター』vol.132、2000年9月、
pp78-96
- 金子大輔・大谷 尚(1999)
フリースクールにおけるコンピュータとインターネットの利用を対
象とした質的研究
−一般の学校との学校文化の差異に着目して−『日本教育工学会第1
5回大会講演論文集』pp113-114
- 大谷 尚(1999)教育実践研究に
おける「研究仮説」設定の問題の検討『日本教育工学会第15回大会講演
論文集』
pp291-292
- 大谷 尚(1999)
多様化する教育実践を対象とする研究手法としての質的研究の意義と課題
『日本教育工学会第15回大会講演論文集』
pp55-56
- 大谷 尚(1999)
国際化・情報化に対応した教育政策の転換と学校教育の展開 −学習指導
要領への国際化・情報化教育政策の反映−『先進工業国における現代都市
社会の諸問題に関する調査報告書』社団法人中部開発センター、pp29-42
- 大谷 尚(1999)「質的研究」の
文脈からみた日本の授業研究の位置づけに関する試論
−研究成果の交流と共有を展望して−『教育方法学研究』24
29-37
- 大谷 尚(1999)
総合的な学習の展開と情報手段の活用 −これまでの学習文化をみ
つめ新たな学習文化を創造するために−『総合人間科の開発過程の評価に
関する事例研究』平成8年度−10年度科学研究費補助金
基盤研究(B)(2) 研究成果報告書(研究代表者 田畑 治)1999
91-100
- 大谷 尚(1998)日本の学校教育
をめぐる体制を考える
−学校と地域社会を考える手がかりとして−『先進工業国における現
代都市社会の諸問題に関する調査報告書.社団法人中部開発センター.1998.
1-11
- 大谷 尚(1998)
インターネットの教育利用における予期しなかった結果に関する一考察
−教育関係者のメーリングリストへの海外からの不適切な要求のメールの
事例をとおして−『名古屋大学教育学部紀要
−教育学−』45(1).1998.99-112
- 大谷 尚・金子大輔(1998)
フリースクールにおけるコンピュータとインターネットの利用を対象とし
た質的研究
−一般の学校との学校文化の差異に着目して−『日本教育工学会第1
4回大会講演論文集』673-674
- 大谷 尚(1998)
授業に対する質的アプローチが教師研究において果たす役割『日本教
育工学会第14回大会講演論文集』(課題研究「授業研究と教師研究の接
点」)219-222
- 大谷 尚(1998)
「質的研究」の文脈からみた日本の教育実践を対象とする研究の位
置づけについて.中部教育学会第47回大会.1998.7.愛知教育大学
- 大谷 尚(1998)
電子メールが利用者の情意的・認知的
な態度におよぼす影響の検討
−感情的なメールをうむメディアとしての電子メールの特性の分析−
『日本科学教育学会年会論文集』22.
61-62
- 大谷 尚(1997)現代社会の中の学校
−現代都市社会の中の学校と若者の都市行動を考えるてがかりとして−
『先進工業国における現代都市社会の諸問題
報告書』社団法人中部開発センター.1997.47-64
- 大谷 尚(1997)子どもの成長と
コンピュータ『子とともに』財団法人愛知県教育振興会.22-27
- 大谷 尚(1997)
情報ネットワークと大学 −ネットワーク社会における行動と新たな知
のあり方を考える『大学と教育』18-28
- 大谷 尚(1997)
質的観察研究とその知見の一事例
−教室における新しいテクノロジーの文化的同化の理論化−
『教育工学関連学協会連合第5回全国大会講演論文集(第一分冊)』
(課題研究?「教育研究方法論[?]」)37-40
- 大谷 尚(1997)
情報ネットワークの教育利用と学校文化
−インターネットが学校にもたらすもの−日本教育方法学会第33回
大会発表要旨(課題研究?「情報ネットワークと教育方法」)p82
- 大谷 尚(1997)
インターネットは学校教育にとってトロイの木馬か −テクノロジ
ーの教育利用と学校文化−『学習評価
研究』29.1997.42-49
- 大谷 尚(1996)
コンピュータが小学校や中学校にもたらすもの『名古屋大学情
報処理教育センター広報』1996.12
.pp4-9
- 大谷 尚(1996)
学校教育におけるコンピュータ利用の特質、問題、課題の解明を目
的とする質的観察研究
−質的データ分析とその適用−『日本教育工学会第12回大会講演論
文集』(課題研究?「教育工学の研究方法論[2]」)237-238
- 大谷 尚(1996)
コンピュータは教室に何をもたらすか −コンピュータを用いた授業を
対象とした観察研究と分析の必要性−『戦
後50年、いま学校を問い直す(教育方法25)』(日本教育方法学会編).明
治図書.1996.129-139
- 大谷 尚(1996)コンピュータが
教室にもたらすもの『教育と医学』500 1996 pp64-69
- 大谷 尚(1996)
情報リテラシーの基底としての学校教
育における「情報」の機能と意義の検討『日本科学教育学会年会論文集』20.41-4
- 大谷 尚(1995)学校教育におけ
るコンピュータ利用を対象とした質的研究のためのコードワードの機能と特性
の検討『名古屋大学教育学部紀要
−教育学科−』42(1)1995
- 大谷 尚・柴田好章(1995)名古
屋大学教育学部と附属学校におけるインターネット利用の試み
−学部、大学院、附属中・高等学校のための情報環境の整備・充実とその
運用について−『名古屋大学教育学部紀要
−教育学科−』42(1) 1995 213-227
- 大谷 尚(1995)コンピュータを
用いた授業を対象とする質的研究の試み『日本教育工学雑誌』18(3/4)
1995 pp189-197
- 大谷 尚(1995)
米国の留学・高等教育情報システムの現状
−カレッジ・ボードを中心に−『留学交流 』7(7) 1995 pp6-9
- 大谷 尚(1994)番組制作におけ
る情報の構成方法・伝達方法の大学授業との差異について『平成5年度放
送利用の大学公開講座テーマ研究報告書』放送教育開発センター 1994
pp1-20
- 大谷 尚(1993)主体的学習のた
めのパソコンの利用『NEW教育とマイコン』学習研究社 1993.10
pp38-41
- 大谷 尚(1993)『現代学校教育
大事典』(奥田真丈・河野重男監修)ぎょうせい 1993.9(担当「SD
法」「データ処理」「トレース機能」「ファミリー・コンピュータ」「メッセ
ージ」)
- 大谷 尚(1993)監訳 アンドリ
ュー・エフラット著「カナダの中等教育の特質と問題」『中等教育研究
第4号 特集「中等教育改革の課題:世界と日本」』1993.3 pp53-66
- 大谷 尚(1993)
日本の教育/カナダの教育
−カナダの学校生活と帰国子女問題−『オーロラ』5(カナダ国内
誌)1993 pp10-12
- 大谷 尚(1993)日本の教育/カ
ナダの教育
−カナダの教育についてのいくつかの補足−『オーロラ』4(カナダ
国内誌)1993 pp12-14
- 大谷 尚(1993)日本とカナダの
教育改革その2
−カナダの教育問題とその改革の動き−『オーロラ』3(カナダ国内
誌)1993 pp12-14
- 大谷 尚(1993)日本とカナダの
教育改革その1
−日本の学校教育の改革の動き『オーロラ』2(カナダ国内誌)
1993 pp10-12
- 大谷 尚(1993)
カナダの教育のこれまでとこれから『オーロラ』1(カナダ国内誌)
1993 pp8-10
- 大谷 尚・河合優年・鋤柄増根
(1992)学校間国際パソコン通信の中・高等学校における教育利用の効果と
影響に関する評価研究『電気通信普及財団研究調査報告書』6 1992
pp152-160
- 大谷 尚(1991)
大学生のレポートにあらわれたコンピュータの教育利用に関する先
入観の分析『名古屋大学教育学部紀要
−教育学科−』37 1991 pp65-77
- 的場正美・大谷 尚・川嶋太津夫(1991)
本学部における授業方法の事例分析『大学の授業方法・授業形
態の改善と充実
−教育研究学内特別経費報告書−』1991.3 pp33-58
- 安彦忠彦・的場正美・浅沼
茂・大谷 尚・川嶋太津夫(1991)授業方法の改善の視点と方向『大
学の授業方法・授業形態の改善と充実
−教育研究学内特別経費報告書−』1991.3 pp75-94
- 大谷 尚(1991)
中・高等学校におけるコンピュータの教育利用と教育課程の情報化
『中等教育研究
第1号 特集「中等学校における教育の情報化」』名古屋大学教育学部
1991.3 pp11-50
- 大谷 尚(1990)
モーショントラックの活用『NEW教育とマイコン』学習研究社
1990.9 pp110-113
- 大谷 尚(1989)
授業研究の一手法としての逐語記録に対する計量的な分析について
『名古屋大学教育学部紀要
−教育学科−』36 1989 pp327-338
- 大谷 尚(1988)
BASICプログラミング教育におけるひとつの試み
−熟考し確信をもってからそれをコンピュータで確認するプログラミング
の学習方法とそのための教材(テキスト)の開発−『長崎大学教育学部大
学教育方法等改善研究プロジェクト報告書』1988 pp70-99
- 大谷 尚(1988)
教員養成大学・学部における教育実践・教育工学センターの教育実
習への関わりに関する調査
『長崎大学教育学部大学教育方法等改善研究プロジェクト報告書』
1988 pp102-123
- 大谷 尚・八田昭平(1987)コン
ピュータを用いた授業(逐語)記録の分析手法の研究『日本教育工学雑
誌』
11(2/3) 1987 pp117-131
- 大谷 尚(1987)
コンピュータ導入に失敗しないために『マイコンレーダー』第一法規
1987.5 pp48-49
- 大谷 尚(1987)
授業分析におけるコンピュータの利用『遥』ぎょうせい 1987.6 pp80-81
- 山口康子・大谷 尚(1986)日本
語の発音指導のためのビデオ教材の開発と評価
−音声のない世界を体験させることをとおして−『長崎大学教育学部
教科教育学研究報告』9 1986 pp113-126
- 古田庄平・大谷 尚(1985)音楽
的聴音能力の実態調査に基づく読譜指導『長崎大学教育学部大学教育方法
等改善研究プロジェクト報告書』1985 pp116-128
- 大谷 尚(1985)パーソナルコン
ピュータによる授業記録分析システムのデータ形式とデータ作成の効率化につ
いて『長崎大学教育学部大学教育方法等改善研究プロジェクト報告書』
1985 pp181-191
- 大谷 尚・松原伸一(1984)出現
語の頻度分布にもとづく授業の特徴化について『電子通信学会教育技術研
究報告』1984.12 pp1-6
- 大谷 尚(1984)パーソナルコン
ピュータを用いた読譜指導のためのCMIシステム
−音楽的聴感覚調査とそのフィードバックシステム−『日本教育工学
雑誌』9 1984 pp71-86
- 大谷 尚(1984)虚構の教材に関
する一考察
−虚構の録音教材をめぐって−『長崎大学教育学部教育科学研究報
告』31 1984 pp45-55
- 大谷 尚(1982)ワードプロセッ
サとパーソナルコンピュータによる日本語処理
−教育情報処理における活用のために−『長崎大学教育学部附属教育
工学センター年報』3 1982 pp26-36
- 大谷 尚(1982)パーソナルコン
ピュータを用いた音の機能を持つCAIシステム
−算数モジュール教材の開発−『日本教育工学雑誌』7 1982 pp87-97
- 菊川 健・大谷 尚(1982)
マイコンの教育利用の問題点『科研総合(A)
教育情報処理のための言語の標準化に関する研究
昭和56年度研究成果報告書』1982 pp87-105
- 大谷 尚(1982)
読譜指導のためのCMIシステムの開発
−教育情報処理の具体的検討−『長崎大学教育学部教科教育学研究報
告』5 1982 pp23-238
- 大谷 尚(1981)教育情報処理に
おけるマイコンの利用
−マイコンのファイル交換について−『科研総合(A)
教育情報処理のための言語の標準化に関する研究 第2年次中間報告』1981
pp9-16
- 大谷 尚(1981)音楽のCAIシ
ステムの開発のための基礎的考察『長崎大学教育学部教科教育学研究報
告』4 1981 pp343-352
- 大谷 尚(1980)教育学学術文献
情報に関する研究
−ERICを用いたビブリオグラフィックな調査−『長崎大学教育学
部教科教育学研究報告』3 1980 pp257-267
【一覧に戻る
| 次へ】
口頭発表(講演論文のあるも
のは、上の「論文・報告書」の項目に掲載し、ここには掲載していません.
)(おまけに現在、未整理です!)
【一覧に戻る
| 次へ】
- 大谷 尚(2002)教育工学におけ
る教育実践研究の課題
日本教育工学会シンポジウム2002「学校との共同研究・研究支援の
あり方を問う」、東京工業大学、2002年6月8日
その他の著作物
(現在、ここには掲載していません
)【一覧に戻る
| 次へ
】
WWWページ
(現在、ここには掲載していませ
ん)【一覧に戻る
】
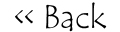
![]()