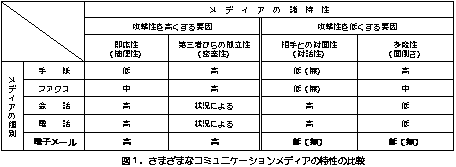
大谷 尚
OTANI, Takashi
名古屋大学 教育学部
School of Education, Nagoya University
〈要 約〉 電子メールを用いたコミュニケーションでは、しばしば、攻撃的なメール、非礼なメール、感情的なメールが送付されることが知られている.本研究は、そのような問題を、コミュニケーションメディアとコミュニケーション手段しての電子メールの特性を分析することによって検討し、情報メディアの教育利用に関する提言をおこなう.
〈キーワード〉インターネット、コミュニケーション、メディア、電子メール、感情
1. はじめに
インターネットの利用が盛んになり、学校教育でも、電子メールがひんぱんに用いられるようになってきた.しかし電子メールを用いたコミュニケーションでは、しばしば、攻撃的、非礼、感情的なメールがやりとりされる.そして、このことが問題視されながらも、その明確な理由や背景は十分論じられてこなかった.
本研究では、そのような問題意識から電子メールのメディアとしての特性を分析し、感情的・攻撃的なメールの背景を明らかにする.
2. 感情的・攻撃的なメールの発信者
これらが、日頃から感情的・攻撃的な人によるのなら、それはメディアの特性とは関係がない.しかし、日頃はていねいな人からこのようなメールが発信されたり、会うといつもどおりていねいなのに、メールでだけ感情的な発信がなされ続けるケースもある.これらのケースでは、電子メールというメディアが発信者のコミュニケーションに影響を与えており、ネットワークと現実とで、比喩的な意味ではあるが一種の人格の分裂のような状態が生じている(大谷
1996,
1997).
3. 背景としての電子メールの特性
このようなメールが電子メールのどのような特性によるのかを考察し、いくつかの要因を抽出した.
(1) 即応性(後述の(4)とは、同一の特性の逆表現)
電子メールでの応答は、熟慮する間もなく、その場できわめて早く行える.
(2) 第三者からの孤立性
電子メールでの発信内容は第三者からは見えない.(これはちょうど、普段穏やかな人が、自動車の運転中に、他の車や歩行者を乱暴にののしることがあるのと似ている.)
(3) 相手との対面性
電子メールでのコミュニケーションでは相手の顔が見えず、声が聞こえない.そのため、こちらの発信内容がどのように受けとめられているかのフィードバックを得られない.
(4) 発信の手続きの多段性
郵便では手紙を書いて郵送するまでの過程は他段階であり、それが反発を思いとどまらせる場合もあろうが、メールでは一瞬に発信でき、その機会を得にくい.
4. 他のコミュニケーションメディアとの比較
これらの特性と攻撃性との関係を考えると、(1)(2)は攻撃性を高くする要因であり、(3)(4)は攻撃性を低くする要因であるといえる.この諸特性に着目してさまざまなコミュニケーションメディアを比較した(図1).これによると、他のすべてのメディアでは、攻撃性を高くする要因が高くても同時に攻撃性を低くする要因が高い.それに対して電子メールは、攻撃性を高くする両要因がともに高く、攻撃性を低くする両要因がともに低いという、きわめて特異なコミュニケーションメディアであることが明らかになった.なお、この比較・分析方法は、今後新たに出現するメディアにも適用可能である.
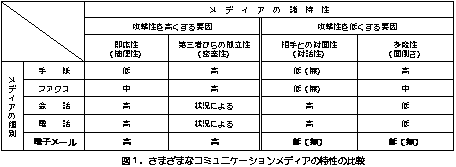
5.
もう一つの背景:他者理解と自己表現の手段としての言語と電子メール
ところで、ネウストプニー(1988)は、外国語を話す時に、「コミュニケーション上のコントロールを失い、自分の感情の爆発を防げなくなることがよくある」と指摘している.これは、外国語での不十分なコミュニケーション能力のために、母語でなら可能な相手の豊かな理解や豊かな自己表現が行えず、直接的、皮相的、表面的な理解や粗暴な感情表現に陥りやすいためだと考えられる(図2).
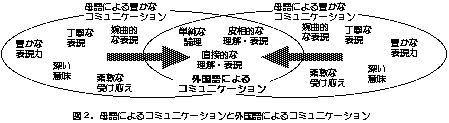
このことは、電子メールの場合も同様だと考えられる.つまり電子メールでは、語法、文法、表現力(たとえば笑いや謝罪などの表現)などが未発達であり、あるいは利用者が充分身につけておらず、こまやかで穏やかな表現ができず、それができないことがさらに誘因となって、いきおい直接的な表現になるなどのために、上述のような「比喩的な意味での一種の人格の分裂あるいは多重人格化」が起こるのだとも考えられる(図3).
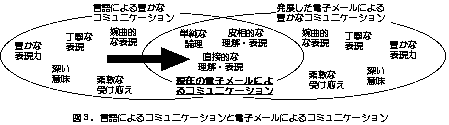
この観点に立つと、電子メールにも豊かな表現力を持たせ、それを利用者が活用することが、感情的・攻撃的なコミュニケーションを防ぐために有効だという仮説を立てることができる.その意味では、顔マーク(スマイリー)の適切な活用や、近年可能になってきたメール本文での書式付きテキストの使用など、メールに豊かな表現力を持たせることが、この問題の解決に貢献する可能性がある.
6. おわりに
小論では、感情的・攻撃的なメールの背景としての、メディアとしての電子メールの特性を分析した.メディアを利用する際には、その特性を多様な方法で分析し、そこから受ける影響を充分に自覚する必要がある.これは、多メディア、ネットワーク時代の教育で、とくに重視すべき課題のひとつである.
・ネウストプトニー.J.V.(1982)
外国人とのコミュニケーション、岩波書店、pp104-105
・大谷 尚(1996)
情報を交流する能力、河野重男監修、赤堀侃司編『教職研修 心の時代の教育̺5
情報化時代に求められる資質・能力と指導』102-105頁、教育開発研究所
・大谷 尚(1997)
情報ネットワークと大学
−ネットワーク社会における行動と新たな知のあり方を考える−、『大学と教育』1997年10月、18-28
この論文について
この論文は、日本科学教育学会第○○大会( 7 月 29-31
日、東京学芸大学)での口頭発表のための講演論文です.この論文は、日本科学教育学会から刊行される、「日本科学教育学会大○○大会講演論文集」に掲載される予定です.このページには、拙著論文を読んで下さるかたの便宜のために掲載しました.
この論文を引用なさる方へ
この論文集は予稿集として、事前に大会参加者に配布されますが、論文の発表日時は学会当日です.このページへの掲載は、学会大会事務局に6
月 4
日着で郵送した原稿をもとにおこないました.作業は慎重におこないましたが、その際に、誤って原文とは若干異なってしまった部分が絶対にないとはいえません.
この論文を引用なさる方は、このページからではなく、必ず標記論文集から直接に引用して下さるようお願い致します.
その他
名古屋大学 教育学部 大谷 尚
otani@educa.nagoya-u.ac.jp