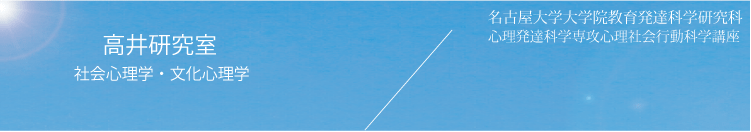
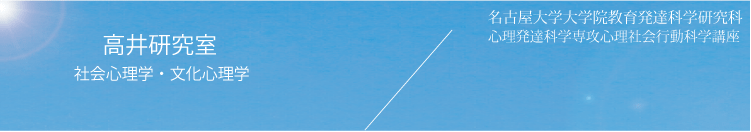 |
→→科研費による研究の概要紹介は,こちらのページでご覧いただけます。
高井研究室では,自他認知について,状況的・関係的文脈における自他認知に関する総合的研究と題した研究を実施しております。対人認知や自己認知が状況的あるいは関係的文脈によって、どのように異なるのかを総合的に追究することが目的です.
上に掲げた目的を果たすために,幾つかのサブテーマを設けてといます。いずれのサブテーマも、これまで“通説”とされていた事象に疑問を投げかけ、独自の見解を提案し、それを裏付けるための実証的なデータを得て、最終的には新たな理論の構築を目指しています.
高井研究室は文化心理学をメインとしているため、比較文化的な視点から研究を進めております。海外から「輸入」された理論を、日本的な独特な理論に置き換えることが目標です.例えば、現在使用されている自己モニタリング尺度は、アメリカで開発されているため、他者に対して自分の存在をアピール・主張するためのモニタリングを測定しています. 上のような話は,何も異文化圏に出なければ出くわさない話ではありません。例えば,最も身近な例では,方言話者に対する印象評定が考えられます。方言話者はどのように認知されるのでしょうか。名古屋弁を話す人が,東京の企業で面接を受ける時に名古屋弁で話すと,採用の確率に影響するでしょうか・・・?(もっとも,採用されるだけの資質が認められていた前提は必要となりますが・・・)。東京出身者が,関西の企業に就職する際に東京のことばで話すと,採否に影響するでしょうか?なぜ,関西出身のコメディアンが多いのでしょうか。これらの問いに対する答えの多くは,コミュニケーションや社会心理学的な研究から示唆されています。 これらは,ことばと人との関係,そして“ことば”が象徴する対象である“文化”が人の生活や人生に及ぼす影響の一部の例です。 更に“文化”が私達に影響している,より厳密には,日本の研究者に対して影響をもたらしている側面もあります。すなわち,欧米で行われた研究成果の“直輸入”です。近年,心理学は飛躍的に進展していますが,背景には欧米における生産的な研究成果の積み重ねがあることは否めません。しかし,前述のように,ことばも文化も違う地域で検証された理論を,そのまま日本文化の枠組みに適用して,日本人や日本文化の問題を説明しようとすることが果たしてどれだけ正しいことだと言えるでしょうか。50%でしょうか?もっと低いのではないでしょうか。 本研究室では,単純に欧米で算出された理論であるからといって,日本文化に適用するのではなく,西洋文化圏からは見えない,東洋文化,日本文化独特の背景を大切にしながら,新しい発見を目指して研究しています。
|