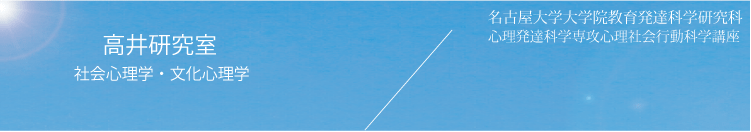
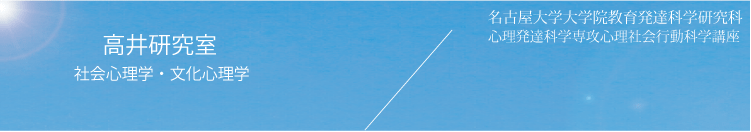 |
このプロジェクトでは,バーンアウトという概念を用いて,集団構成員のやる気やコミットメントの減衰を阻止するために有益な知見を提供することを目的としています。 2009年第一回の打ち合わせを開催しました。現在,関連研究の意識調査を実施中です。調査票を受け取られた方は,ご協力お願いします。
いかに構成員を守りながら,生産的な集団を維持するか。いかに構成員のバーンアウトを防ぐかという点について,実証的に考えます。以下,部分的に詳細な説明を記します。 【研究の枠組みにおける“接近型”と“回避型”】 また,過度なモチベーションの向上は時として,将来的なモチベーションの急落を招く要因としても考えられてきています。よって,モチベーションのバランスを取ることが大切である,といった,間接的(あまり現実的ではない)結論に達することがあります。よって,問題の根本的な解決につなげる知見の提供には結びつかないものもみられます。そもそも,モチベーションを操作するためには,対象者にある程度の動機付けが備わっていることが大前提となることもあります。 ・回避型研究の必要性
理論をこねまわすような研究よりも,就労環境でどのようなことが発生するのか,実社会でどのような知見が必要かを最優先した研究を行います。理論研究を軽視するものではありませんが,社会還元しやすい研究を行うことを至上の目的として据えています。
|