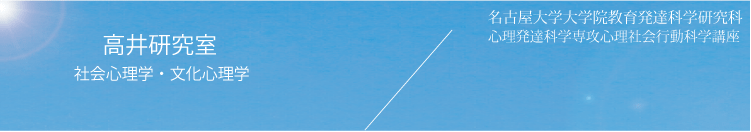
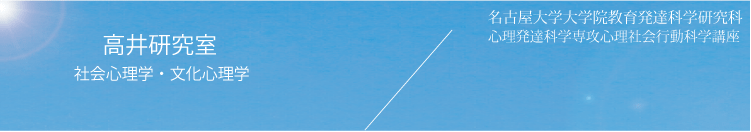 |
日本人は“ふつう”という言葉をよく使用しますが,これにはどのような意味が込められているでしょうか。少なくとも,情報発信者である場合,自らが使用する“ふつう”の定義や解釈はある程度明確なものであると考えられます。しかし,ひとたび“ふつう”と評価される側に立つと,その解釈可能性は大きく幅を持つのではないでしょうか。
“ふつう”という評価に,人がどのような意味を込めるのか,少なくとも,人がどのような印象をもって“ふつう”という表現を使用しているかという問いは,これまでにも社会心理学者の関心を集めてきました。近年では,我が国の研究者によって,少しずつ,ふつうに対して日本人がどのような印象を持っているかが明らかにされてきています。 一般的に,“ふつう”ということばに対する印象は肯定的なものであると考えられていると,先行研究の結果は一貫して指摘しています。このことは,もはや古典的とも言える“出る杭は打たれる”という日本文化を表象する表現からもうなずけることです。“出る杭”が打たれてしまうので,打たれないために“ふつう”であろうとすることや,“ふつう”であることが肯定的に受け入れられている社会的背景があると考えられるためです。 しかし,この話は“評定者”と“被評定者”とでは大きく事情が異なるのではないでしょうか。すくなくとも,我々が“ふつう”と考えるものには,数種類のスタンダードが存在し,それらのスタンダードは状況や文脈によって使い分けられているのではないでしょうか。統計学的な話であらわされるところの,平均的なもの,と“ふつう”との間,あるいは“中央値”と“ふつう”との間には,大きな違いがあるのではないでしょうか。
“君はふつうだね”と言われたとき,われわれはどのように感じるでしょうか。どのように評価されていると感じるでしょうか。この解釈のズレは,個人と個人のコミュニケーション上で大きな誤解を招く要因となりかねません。むろん,誰から“ふつう”と評価されているのか,どのような人に“ふつう”と評価されているのかという問いも,われわれが“ふつう”ということばから得る印象や解釈を考える上では重要な要因となります。 本研究では,これまでは情報発信者視点で検討されてきた“ふつう”ということばについて,情報の受け手,もっと具体的には,被評価者の視点から“ふつう”であるということに対する認識を明らかにすることを目的としています。むろん,上で述べたような,評価者との関係や,社会的文脈(地位の相違など)も視野に入れた検討を行っています。使用するものとしては,概ね一貫して,肯定的な印象を想起させられる“ふつう”という評価ですが,“被評定者”視点から考えて,“ふつう”はどのような意味をもつのでしょうか。 日本文化は,欧米人の目から考えると,集団主義的で,個々人のユニークさが乏しい文化としてとらえられがちです。しかし,本当にそのような通説が的確なものであるのか,ユニークさへの追求が現代日本において欠落しているのかという点は,疑問が残ります。我々の文化や社会の実態がどのように変化しているのか,また,現在どのような特徴を有しているのかという根本的な問いに一つの回答を提供することを目的としています。そのような目的を達成するために,本研究では,“ふつう”という,きわめて一般的で“ふつう”な表現に対するわれわれ日本人の認識を解明していきます。
|