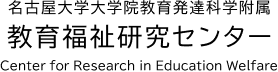GREETING

あらゆる人々の
連携と連帯の中心に
センター長
名古屋大学大学院教育発達研究科・教授
石井 拓児
「社会的排除(Social Exclusion)」という概念が生み出されたことにより、社会において不平等や不利な立場にある人々の問題が可視化されるようになりました。児童虐待問題やヤングケアラー問題は、子どもの安全・安心に生きる権利や子どもが子ども期にとうぜん保障されるべき子どもらしく生きる権利を奪うものです。近年、やや数値は改善傾向にあるものの子どもの貧困の問題は依然として深刻です。
こうした問題群をとらえるとき、いま、教育と福祉を横断的にとらえ実践的課題に応答するための理論研究の枠組みを構築していかなくてはならないと強く感じます。第一に、社会的包摂に向けた教育法・制度的要請があります。児童福祉法が改正されているほか、児童虐待防止法・障害者差別解消法・子どもの貧困対策推進法・普通教育機会確保法・高等学校修学支援法・高等教育修学支援法・スポーツ基本法等々が制定されてきています。これをいかなるものとして制度設計・社会実装していくのかが問われています。
第二に、こうした法制定状況をふまえ、学校教育・社会教育施設や福祉施設における新たな実践的課題も生まれてきています。障害者差別解消法に定められた合理的配慮とは具体的にどういった水準で確保されなくてはならないかを明らかにすることはきわめて重要な研究課題です。どこでも「部活動の地域移行」が政策課題となってきていますが、スポーツ・文化を享受(enjoy)する権利はどのようにして保障されるのか、これまでスポーツ・文化の権利を十分に保障されてこなかった女性や障害者の権利をいかにして回復するのか、本格的な研究と調査が必要です。
このとき、「社会的排除」をめぐる権利の衝突が起こることは避けることができません。むしろ、こういった権利の衝突によってこそ人権・権利の水準は常に引き上げられ、社会の前進と私たちの生活水準・幸福水準は向上してきたというべきでしょう。紛争等社会的課題の解決や権利の調整・調停のための理論やアイデアをより高い水準で発信していきたいと思います。
そのためには、子どもの権利条約や女性差別撤廃条約、人種差別撤廃条約、障害者権利条約といった国際人権法の新しい展開をふまえ、新たな合意水準を追究していかなくてはなりません。と同時に、こうした新しい地平を切り開いてきた教育思想や教育運動の歴史から学ぶことも重要だと私たちは考えています。 さまざまな分野や領域において、社会的に不利な立場にある人々の社会的包摂に向けて懸命に支援し活動をしている行政機関や相談機関、医療機関、教育施設・児童施設、ボランティア、NPO・NGO等の民間団体、労働運動・教育運動団体、個人、あらゆる人々との連携と連帯を生み出す中心(文字通りのセンター)になりたいと願っています。
PROJECT
- 学校教育部門
- 学校教育における社会的排除の問題を念頭に、社会的包摂に向けた理論的・実践的課題を追究します。不登校、障害、性別不合・SOGIE、人種や国籍、貧困、ヤングケアラーといった諸々の課題の解明に取り組みます。また、国内外における学校教育制度の歴史的変遷や教育思想・教育運動の存在にも目を向け、社会的包摂や連帯といった価値理念をめぐる社会基盤の形成過程を明らかにします。
- 社会・生涯教育部門
- 社会教育・生涯教育の観点から社会的包摂をめぐる理論的課題・実践的課題を究明します。子ども・若者支援や障害者支援等、学校教育・社会教育・職業教育における切れ目のない支援のあり方や学校から職業へのスムーズな移行を支える仕組みを検証します。自治体、住民団体、企業、NPO等民間団体との連携をすすめつつ、自治体政策づくりやまちづくり、学習運動・住民運動、労働運動、障害をもつ人々の大学・高等教育機会の提供のための実践にも着目します。
- 教育臨床部門
- 子どもの権利侵害状況に目を向け、子どもの権利救済ならびに子ども支援、家族支援のあり方を追究します。学校教育・社会教育施設、児童福祉施設、子どもの権利擁護機関、医療機関、行政機関等との連携のあり方、スクールロイヤーやスクールソーシャルワーカー、子どもアドボケイター等の制度措置状況およびその実践的課題を明らかにするとともに、子どもの権利条約の価値理念を深め、子どもの権利に関する国内法ならびに自治体における条例や子どもの権利救済機関の設置状況などモニターします。また、海外の教育福祉研究センターや包括的な子ども行政組織とも連携し、海外の制度状況を調査します。
- スポーツ・環境部門
- 人間の健康と幸福の実現に果たすスポーツの役割に着目し、スポーツの権利、スポーツの権利保障のための具体的な諸制度や環境整備・条件整備のあり方を追究します。部活動の地域移行・地域展開の状況を調査するとともに、障害者や女性のスポーツからの社会的排除の問題、スポーツ場面における虐待や不適切な指導の問題にも取り組みます。 スポーツを通じた人間形成、子ども・青年期のサークル活動(課外活動)の意義、社会的包摂・連帯やコミュニティの形成に果たすスポーツの役割を明らかにします。