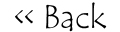大谷
尚(おおたに たかし)

名古屋大学 大学院 教育発達科学研究科 教授(学校情報学)
以下は、ちょっとナラティブな自己紹介です.
このページにはささやかな試みがな
されています.それは、自分が過去に関わった人や組織の現在のページへとリンクするというものです.たとえば、大学院時代にお世話になった先生方の現在の
ページへリンクしているばかりでなく、自分の生まれた産院のページへまでリンクしています.
このことの意義は、うまく表現できませんし、このページをご覧になる方には無関係かもしれませんが、自分と、過去に点あるいは短い線でつながりのあった
方や組織の現在の姿へとリンクすることで、そのつながりを長い線にできたらという試みとでもいったらいいでしょうか.
最後に更新したのは 2019.4.22
です.ただし内容はあまり更新せず,定年退職に伴う所属の変更などをしています.
生年月日等(ここではかんたんに.くわしくはさいごに)
- 生まれた時と場所
1953 年 10 月 29 日 東京渋谷の日赤産院(現在の日赤医療センター産科?)生まれです.
- その後
生まれてから小学校3年まで、東京都目黒区自由が丘で育ち、小学校4年になるときに神奈川県海老名市(当時の高座郡海老名町)に家族とともに転居しました.その後、長崎大学に赴任するまで、同市に居住していました.
- 現在の家族
妻(結婚は1980 年.2005
年に銀婚式でした!)と2人の娘です.長女は某国立大学医学専門学群出身で現在産婦人科医師.次女は某私立大学外国語学部英語学科出身で現在,私がオー
ナーではない国内某最大手ホテル勤務.2人とも結婚しています.大変仲良しの家族であり、価値観を共有している家族です.
学歴など(なんと幼稚園から!)
- 1958
玉川神の教会附属 子羊幼稚園(現在の玉川子羊幼稚園)に入園(うーんとかわいかった頃)
目黒区在住でしたが、小さな川を越え、世田谷区側の同幼稚園に通っていました.
幼稚園の頃のことはいくつか覚えていますが、幼稚園より前のことはあまり覚えていません.どんなふうに暮らしていたのでしょう...
- 1960
目黒区立 緑ヶ丘小学校
(校舎写真)(3年まで)
幼稚園のときの目黒区側の子ども達と一緒に、学区の緑が丘小学校に入学しました.この小学校は、当時、目白にある本家の「目白の学習院」に対して「目黒
の学習院」と謳われたほどの有名公立小学校でした.たしかに、定期をもって通っているクラスメート、つまり親戚や知人宅に住民票を移す「寄留」をしての越
境入学者が何人もいました.先生方は栄転の末に着任される方ばかりだったようです.同校の卒業生に、ピアニストでフィンランド国立音楽院シベリウス・アカ
デミー教授の舘野泉氏、俳優の浜木綿子氏などがいます.(と聞いたのをそのまま信じています.)(浜木綿子氏は、1980年ごろに、銀座の洋服屋さんでお見かけしました.大女優なのに普通の感じの方で、けばけばしいところがまったくなく、敬服致しました.)
この学校のページを今みると、校舎がすごいです! 昔はこんなじゃなかった(あたりまえですが).なおこの頃、自由が丘にいらした市川先生という方にピ
アノを習っていました.いつもお着物をお召しの大変上品な方で、レオニード・クロイツァー門下でいらっしゃいました.(ということは、市川先生は、ラ・カ
ンパネラの演奏で脚光を浴びたピアニスト、フジ子・ヘミング氏と兄弟弟子(姉妹弟子)なのですね.ということは、フジ子・ヘミング氏は、私の叔母弟子なの
ですね.)
- 1963
海老名(えびな)町立海老名小学校に転校(4年)
現在、東名高速道路の海老名サービスエリアのある海老名は、奈良から平安初期まで海老名耕地という大耕地があって、相模の国の国府があったところです
(現在でも海老名耕地と呼んでいます).国分寺、国分尼寺の跡もあります.都会の学校から、田圃のたくさんあるこの田園地域の学校に転校しました.自宅の
近くに、4年生の通える学校はなく、電車で一駅乗って学校に通いました.朝、田圃の中を通る用水路に土管や瓶などをしずめておき、帰りにそれを引き上げ
て、中二杯っているザリガニを捕ったり、捕ったザリガニを餌としてワラの先に結びつけ、さらにザリガニを釣ったりしました.担任の今福先生は、当地出身
の、当時有名だったNHKの今福アナウンサーのいとこにあたられる方で、今福アナウンサーと似た、ふっくらとした穏やかで鷹揚な方でした.そして、都会か
ら来た生意気な少年を暖かく見ていてくれました.なおこの少年は、現在では、子ども時代は ADHD
だったのではないか、そして今でもそうなのではないかというのが、医学生であった長女の診断であり、現在では皆がそう信じています.
- 分離独立で海老名町立柏ヶ谷小学校に移籍(5・6年)
それまで海老名小学校柏ヶ谷分校という3年生までの分校が、独立した小学校になり、柏ヶ谷地区の子どもたちは、そちらに移籍しました.電車通学は終わりました.児童会長などをした記憶があります.
- 1966
海老名町立海老名中学校に入学
この学校は上述の海老名小学校の隣にある学校で、ふたたび電車通学が始まりました.吹奏楽部に所属して、中学校に進学したらやりたいと小学校の時から
願っていたトロンボーンを吹いていました.生徒会活動も一生懸命やっており、生徒会長もしました.ノートがきらいで、中学校3年間で一度もノートを取りま
せんでした.また、2年生の1年間、決意して、お昼のお弁当を左手で食べ続けました.今でも左手でお箸が使えますから右手を怪我しても食事だけは困りませ
ん.(たいした意味があるのか...)
この頃、生意気にも大学は東京芸大の楽理科に行きたいと思うようになりました.海老名に引っ越してから、近くに先生がいなかったために中断していたピア
ノのレッスンを、高校に入ったら再開して受験準備をしようと考えていました.しかし公立高校の学区外入試に失敗し(倍率1倍だったのになぜ落ちるの
か...)、私立高校に進むことになります.
- 1969 私立桐蔭学園高等学校に入学
公立高校入試に失敗して通うことになったこの学校は家から遠く、上記のようなピアノのレッスンの再開はできませんでした.しかし音楽学にはまだ興味があり、通学にかかる時間を生かして、楽典、作曲法、和声学などの本を読んでいました.
この学校は創立まもない学校で、私は5期生でした.教員の数が絶対的に不足しており、都内の大学の博士課程の大学院生を非常勤講師に招いて授業をさせて
いました.このころ私は「教育」について考えるようになりました.同時に、この大学院生の方々に影響を受け、自分も大学院に進んで研究をしたいと思うよう
になりました.
ただし、その中のお一人でいらした博士課程の院生で非常勤講師に来ていらした和田守先生(現在大東文化大学学長)
にこのことを話すと「君は教育学をやりたいのか、教育について考えたいのか、どちらですか?」とたずねられました.「その二つは違うのですか?」とたずね
ると「違うのです.教育学をやりたいのではなく教育について考えたいのなら、教育学科には進まないほうがいいのです.」と言われました.しかしその時の私
には、その意味がよく理解できませんでした.
クラブは、吹奏楽部でクラリネットを吹いていましたが、電車とバスを乗り継いで大変な時間をかけて通っていたため、続けるのが困難になり、2年になると
きに辞めました.しかし私が3年のとき、野球部が夏の全国高校野球大会(甲子園大会)に初出場することになりました.県大会の時から応援団を組織して活動
していましたが、私は吹奏楽をやっていたので、吹奏楽との連携の役割もあり、甲子園には、もちろん大学受験そっちのけで応援に行きました.野球部は見事、初出場発優勝をしました.
- 1972 東京教育大学 教育学部
教育学科 教育学専攻に入学
高校時代の希望通り「教育学」を専門とする学科に入りました.しかし1年したころ、高校時代に和田守先生から言われたことの意味が分かりました.そこ
で、当時の東京教育大は転学部が比較的簡単でしたので、転学部しようかとも考えましたが、勇気がなかったためか、オーケストラに熱心だったためか、転学部
はしませんでした.
オーケストラではコントラバスを弾いていました.(ペートーベン曰く「コントラバスこそ、オーケストラでいちばん音楽性の高い人が弾くべき楽器であ
る」.マルクス・アウレリウス曰く「人生は、ダンスよりもレスリングに似ている」.)学科の学生控え室よりもオケの部室に直行して、いつも楽器を触ってい
ました.トレーニング・コンダクター(今風にいえば「トレコン」.当時のことばで「学生指揮者」)もしていて、自大学のオーケストラの他、たいへんあつか
ましいことに他大学(中央大学)にも棒を振りに行っていました.こういうのを若気の至りというのでしょう.
専攻は、教育課程(カリキュラム)論でしたが、教育学の勉強をしないで音楽ばかりやっていたので、卒業論文は「芸術の技術の教育に関する一考察 −斎藤
秀雄の『指揮報教程』を中心として−」を書きました.指導教官は小野慶太郎先生でした.小野先生は、「カリキュラムとは、人間の歩む道のことだ.己(おの
れ)の道を歩んだ者でなければ、カリキュラムは語れないのだ.だから、君が何をやると言っても、俺は決して止(と)めないぞ.」と言って下さいました.
- 1976 筑波大学
大学院
博士課程教育学研究科(5年一貫性の博士課程です.その後、博士課程人間総合科学研究科に改組)に入学
所属は教育内容講座で指導教官はやはり小野慶太郎先生.小野先生は禅に打ち込んでいらした方で、ゼミは禅問答のようでした.私はそれを心からエンジョイ
しており、「大学院ってこんなに面白いところだったのか!」と喜んでいました.博士課程の修士取得までは「ペスタロッチの直観」について、修士取得後は、
Martin Heidegger をやっていました.
大学院の3年目に、筑波大学学術情報処理センターにわらじを脱いで、コンピュータそのものやコンピュータの教育利用について指導を受けました.この頃は、まだ実用的なパソコンが出る前で、使っていたのは大型計算機で言語は
FORTRAN でしたが、同センターでは、竹園東小学校で「クラスルーム
CAI」
の実験を始めていました.また、同センターはデータベースについて世界でも先端的な研究機関であり、この環境を生かして、データベースをもちいた
Bibliometrics(計量書誌学)
の手法による教育研究の試みもしました.この時にお世話になったのは、中山和彦先生(現在、筑波大学名誉教授)、及川昭文先生(現在、総合研究大学院大学教授)、堀口秀嗣先生(現在、常磐大学教授)、上田修一先生(現在、慶応義塾大学教授)などでした.その後、博士課程を中退して長崎大学に就職しました.
職 歴
- 1979 長崎大学 教育学部
附属教育工学センター 助手
はじめて関東を離れ、街並みも自然環境もまったく異なるところで暮らしはじめました.職に就いて、さまざまなことを学び始めましたが、当時はまだまだ学生気分が抜けず(今だにですが)、さまざまな方々にいろいろとご迷惑をおかけしたことと思います.
- 1986 長崎大学 教育学部
附属教育実践研究指導センター 助手(センター改組による)
教育実地研究部門という部門ができ、センターが教育実習の事前・事後指導等を担当する方向になりました.
- 1986 長崎大学 教育学部
附属教育実践研究指導センター 講師
この間、長崎大学教育学部のさまざまな先生方との共同研究をしていました.音楽教育の研究のお手伝いもしました.家庭科の学生は、卒論の発表会の直前に
なると統計処理のことで相談にきました.センターの運営、改組などのために働いていましたが、自分のオリジナルな研究としては、コンピュータを用いた授業
逐語記録の分析の試みなどをしておりました.
- 1989 名古屋大学 教育学部
教育学科 教育情報学講座 助教授
標記講座の開設にともない、名古屋大学に移りました.名古屋に移った頃から、コンピュータが実際に教室で使われるようになり、この新しい環境が、学校の
もっている文化的な特性とどのような相互作用を起こし、教師や子どもにどのような影響を与えるのかについて、観察を通した研究を始めるようになりました.
- 1997 名古屋大学 教育学部
人間発達科学科 学校教育科学講座
助教授(教育情報学)(学部改組による)
- 1999 名古屋大学 教育学部
人間発達科学科 学校教育科学講座 教 授(教育情報学)
- 2000 名古屋大学大学院
教育発達科学研究科 学校情報環境学講座
教 授(学校情報学)(大学院組織化(大学院重点化)による)
- 2007-2010 大学院教育発達科学研究科 副研究科長
- 2010-2013 名古屋大学教育学部附属中・高等学校長(併任)
- 2013-2014 大学院教育発達科学研究科 副研究科長・附属中等教育研究センター長
- 2015- 大学院教育発達科学研究科 附属高大接続研究センター長
- 2017-2019 名古屋大学 アジア共創教育研究機構 教授
- 2019- 名古屋大学 大学院教育発達科学研究科 特任教授
現在に至る
在外指導・在外研究等
- 1987
7月-8月 国際協力事業団(JICA)派遣専門家 中国北京市、長春市、瀋陽市、西安市
UNESCO の APEID(Asian Program for Educational Innovation and
Development)の一環として行われたもので、日本の5人の専門家が中国の専門家(大学等の教員)に対して、教育工学について指導できるように技
術移転するプロジェクトです.教育工学を伝えるということについてはもちろん、教育における異文化摩擦について実際に体験した貴重な2ヶ月でした.
- 1988
7月-8月 国際協力事業団(JICA)派遣専門家 中国北京市、昆明市、上海市
同上(上とおなじく、各地方の中国料理も堪能しました.)
- 1991 8月-1992
7月 トロント大学オンタリオ教育研究所(大学院)測定・評価・コンピュータ利用
部門 客員研究員 (Visiting Scholar, Department of Measurement,
Evaluation, Computer Applications, The
Ontario Institute for Studies in
Education(OISE))(国際交流事業団「学者等長期派遣」による)
ここで、コンピュータの教育利用を対象とし、観察を通した質的研究を行っていた
Donald G.Ragsdale 教授(現在、米国ルイジアナ州にある
Northwestern
State University
教授)の研究グループに参加し、質的研究の手法などを学びました.また、北米の学校文化や学校と家庭や社会との関係、また大学院での教育や研究のあり方など、さまざまなことを学びました.
- 2005 3月-2006 3月 トロント大学オンタリオ教育研究所(大学院)教育理論・政策学科 客員研究員 (Visiting Scholar, Department of Theory and Policy Studies in Education, The Ontario Institute for Studies in Education(OISE))(文部科学省「海外先進教育実践研究支援プログラム」による)
教員と学校管理職、教育行政担当者のための大学院レベルの professional development
(専門的発達)のためのプログラムについて調査しました.とくに、教員にとって専門的発達とは何か、どういう意味や意義があるのか、その問題や課題は何か
を解明しようと、教員を対象としたライフストーリー・インタビューを行いました.また、同じ専門職教育である、医学教育、法学教育、神学教育などについて
も調査をしました.(ついでに、Dundas Street 研究、Niagara Escarpment 研究、22 minutes
研究などをしています.)
所属学会
- 1976- 日本教育学会
- 1977- 日本教育方法学会
- 1979- 日本科学教育学会(編集委員会委員
1997-2002)
- 1984- 日本教育工学会(
編集委員会委員
1996-、理事
2001-、企画委員会委員(担当理事)
2000-、研究会委員会委員
2001-,理事 (FD委員会担当)2011- )
- 1993- 中部教育学会
- 2004- 日本質的心理学会(理事 2008-20011,編集委員 2013-)
- 2007- 日本医学教育学会(「医学教育専門家育成・マスターコース設立に関する委員会」委員 2008-2010、「医学教育専門家制度委員会」委員2010-2012、「医学教育専門家制度WG」委員 2012-)
- 2008- 日本総合診療医学会 → プライマリ・ケア連合学会に改組
- 2008- 日本家庭医療学会 → プライマリ・ケア連合学会に改組
- 2010- 日本プライマリ・ケア連合学会
協会・研究団体等
医学教育関係の委員・非常勤講師等
- 2007年 4月− 2009年3月 独立行政法人 国立病院機構 長崎医療センター 「臨床研修管理委員会」委員
- 2009年12月− 現在 独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター「臨床研修管理委員会」委員
- 2014年 4月− 現在 長崎大学病院「臨床研修管理委員会」委員
- 2008年 4月− 2013年3月 長崎大学「大学病院連携型高度医療人養成推進事業GP」委員
- 2009年 4月− 現在 東京慈恵会医科大学 医療人GP「プライマリケア現場における臨床研究者の育成プログラム」指導委員
- 2007年 6月− 2008年5月 日本医学教育学会「医学教育マスターコース検討委員会」委員
- 2008年 6月− 2010年5月 日本医学教育学会「医学教育専門家育成・マスターコース設立に関する委員会」委員
- 2010年 6月− 2012年5月 日本医学教育学会「医学教育専門家制度委員会」委員
- 2012年 6月− 2014年5月 日本医学教育学会「医学教育専門家制度WG」委員
- 2014年 6月− 現在 日本医学教育学会「医学教育専門家制度WG」アドバイザー
- 2011年 4月− 現在 帝京平成大学 大学院薬学研究科 非常勤講師
- 2014年 4月− 現在 広島大学 大学院医歯薬保健学研究科 非常勤講師
- 2014年 4月− 現在 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 非常勤講師(未来医療研究人材養成拠点形成事業)
- 2014年 4月− 現在 三重大学 大学院医学系研究科 非常勤講師(未来医療研究人材養成拠点形成事業)
ふたたびナラティブな私的情報
- 生家の家族
父は愛知県出身、陸軍士官学校卒.砲兵大尉.インパール作戦に従事しましたが奇跡的に生き残り、終戦で戦地から帰国後は、建設・設備関係の会社社員・役
員として働きました.大変に仕事熱心な人でした.日本はまだまだ戦後の復興期で、子どもの起きる前に出かけ、寝てから帰ってきたため、小さいころの父親の
思い出はほとんどありません.母は三重県出身、津高等女学校卒.専業主婦でした.陸軍近衛士官の娘で、親戚の男性のほとんどが軍人、親戚の女性のほとんど
が軍人に嫁ぐという家族でした.このような家庭で私は、「近代的」な規範・価値観を刷り込まれて育ったように思います.このような規範や価値観は、現代の
教育を考えるためには、また、多様な学生と接する上では、さらに自分が子育てをする上では、私にとって障害となることもあったと思います.これを少しずつ
克服するのが、私にとって課題でもあったように思います.
兄弟は二つ上の兄(国内最大の某電器メーカー社員.その後退職)と、私と双子の弟(カレーやスパイスを作っている国内某有名食品メーカー海外事業部長等を経て属託.その後退職)の男3人兄弟です.
- 名 前
「尚」は「たかし」と読みます.字源という辞典によると、この字は、かまどから煙が立ちのぼる様子を表す象形文字で、「高」が物理的に高いことを表すのに
対して、「尚」は、精神的に高いことを表すようです.(そういえば「和尚」や「高尚」などに使われていますが、そのためですね.)名前に負けないようにし
なければといつも思って...いません. (^_^;) この字は、父が士官学校の名簿から見つけたと聞いています.
なお、名字と名前を縦に書くと、おおむね左右対称になります.中学校のときに生徒会長に立候補したときに、ポスターが選挙管理委員会の印鑑の押してある
数枚の画用紙に限られるので、これを生かして、裏に出るように濃く名前を書き、「裏から読んでも大谷尚」と書いて渡り廊下につるしたら、先生に怒られ、壁
に貼らされました.でも、基本的に、左右対称でない、画数の多い重厚な漢字の名前の人がうらやましいです.
- 趣 味
- 音 楽
上述のように小さいときから音楽をしており、大学生時代にはオーケストラや室内楽でコントラバスを弾いていましたが(コントラバスは檜山薫門下の久保田洋氏に師事)、その後ずっと弾いておりませんでした.しかし
2003 年の 2
月に、ふとしたきっかけから、きわめて厳しい(?)オーディションを経て名古屋市民管弦楽団に参加させて頂くことになり、28
年ぶりにコントラバスを弾くことになりました.ドイツの
Marknneukirchen
という町のコントラバス制作者 Johannes Rubner
の新作の5弦バスを
入手し、時間を見つけて練習しています.弓は大学生時代に使っていて 28 年間ケースの中で休息していた Herman Richard
Pfretzchner
です.公務員住宅のため、夜7時までしか楽器が弾けません.しかし夜7時に帰れることはまずありませんので、おかげさまで一時的に朝が早起きになりました
が、その後戻りました..楽器演奏と運搬のためか体重も減りはじめ、皆に「痩せたんじゃない! 大丈夫?」と言われていましたがヽ(^o^)丿、これもそ
の後戻りました.(2004 年に名古屋大学は国立大学法人となり、職員は国家公務員から法人職員になったため、国家公務員住宅を追い出され、2014.8月に、UR の賃貸住宅に転居しました.)
なお、大学生時代からリコーダーも演奏しており、学生時代には、ブリュージュのリコーダー・コンクールで優勝した東京リコーダー・カルテットの松島孝晴
氏に師事していました..その後「ひよっ」て、ウインド・シンセサイザー(管楽器のシンセサイザー)などを吹いています.
そうそう、口笛も大変上手です.数年前に、あるバンドでウインド・シンセを担当したのですが、編曲の都合で、ある曲で口笛を吹くことになったところ、そ
の音域の広さ、音程の正確さに驚嘆の声があがりました(ほんとか).OISEでも、Amazing Whistler!
と言われておりました(ホントです.).しかも吹くだけでなく「吸っても」音が出るという秘技を
有しており、息継ぎの必要なく無限に口笛で曲が吹き続けられるという、一種の奇人変人です.(口笛は、たとえ吸ったときに音が出せても、吹いたときと吸っ
たときとではかなり音程が異なってしまうので、吹いたり吸ったりしながら曲を演奏するのは、そうとう難しいのですよ.)
(2003.4.2追加情報:筒井康隆が「天狗の落とし物」というショートショート集の中で、「黒柳徹子は絶えずしゃべり続けているが、どこで息を吸っ
ているのかと思ったら、なんと息を吸いながらもしゃべっているのだ」とギャグで書いたのですが、黒柳徹子の話では、本当に吸ってしゃべっているそうです.
声紋モニターのようなものを使って分析したら、吸っているところだけグラフが上がっていたということです.彼女の話では、フランスの女優のサラ・ベルナー
ルもラシーヌを朗読するレコードで息を継いでおらず、何カ所が吸って声を出しているところがあることが、自分には分かるとのことです.黒柳家は私が幼い時
に住んでいた自由が丘でした.母と外出すると「ほら、あの男の人が黒柳徹子のお父さんよ」などと言われたこともありましたし、彼女の通っていた「ともえ学
園」は自宅のそばにありました.ひょっとすると、これは自由が丘系呼吸法かもしれません.)(口笛は、その後、2006年にトロント在住時に取れてしまっ
た1本の歯を今だに埋めていないため、音程が不正確になり、今は自慢できない状態です.)
- さまざまなもの(機械類、楽器類、アクセサリーなど)の修理
小学生の頃から、シャープペンシルの修理などをクラスメートに依頼されて得意になってやっていました.直らなくなったものからは部品を取らせてもらい、そ
れもたくさん揃えて持っていました.高校・大学のころは、吹奏楽部やオーケストラの仲間に依頼されるフルート、クラリネット等のキー関係の不具合の分解・
調整や、弦楽器の修理・調整をしていました.フルートもクラリネットもキーを全部はすして組み直すことが簡単にできました.名古屋に来てからは、依頼され
て古い教会オルガンの修理・調整をすることもあります.その他、ヘアードライヤーや掃除機など、必要に応じて家庭電化製品も修理します.家族のネックレ
ス、ペンダント、イヤリングなどのアクセサリー類や、こわれたものはすべて、私のところにまわされます.趣味と特技を生かして感謝されるので、これは有意
義で楽しい仕事です.
- 料 理
自分の包丁を何種類か持っています.料理は家族がお客様です.新しいレシピを開発し,学生を含むいろんな人たちにメールで送りつけ,作った料理の写メが送られて来るのを楽しみにしています.
- 中華料理
上述のように中国各地で仕事をしたことがあるので、本場中国仕込みです.(と言えるのか...)上海に出張するたびに,中華包丁を買って来ます.
- パスタ類
本場シチリア風です.(といってもシチリア系アメリカ人3世の兄弟が書いたパスタのレシピブックを使っているだけです).それ以外に,名作「春の水菜のスパゲティ」,「ツナとゴーヤのスパゲティ」,「ツナとオクラの冷や麦」などのオリジナルレシピもたくさんあります.
- カレー、シチューなどの煮込み料理
料理中にずっとついていなくていいので、仕事をしながらできますし、保存がきくのもメリットです.
- その他
切り干し大根やひじきと油揚の煮物などのお総菜風のものもつくります.その他、パン食を豊かにする具だくさんのスープ、パーティーの持ち寄り料理などの創作料理(食に対する
狭い経験が生んだ独善的料理)、即席の何種類ものお漬け物なども作ります.「おつけものにビオフェルミンの粉末を加えると適切な乳酸発酵が起きるか」という
実験を冷蔵庫内でしたりしました.なお、「ベーグルとスパゲティがあればご飯はいらない!」がモットーで、カナダで「ベーグル専用トースター」(切った面
を焼き、外側は暖めるだけなのです)2台とベーグルスライサー(ベーグルを半分に切るもの)何器かも購入しました.
- 食材購入
アメリカ、カナダなどに出張したときは、食材購入の貴重な機会です.持ち物が少なくても大きなスーツケースを用意し、新聞紙を丸めて空間を埋めて行きます.現地のスーパーマーケットで、あちらでしか購入できない食材を買い込みます(2002年3月のアメリカ出張で購入した食材).ホテルには、丸まった日本の新聞が残ります.ですから、現地の訪問先で予想外に大量の資料を頂いてしまったときなどは、大変に困ります.2003
年 3
月のトロント出張でも、あちらでカバンを購入するはめになりました.
以上です.また追加します.